
好き嫌いが多い、食が細い、食事に集中しないetc.
子育て中なら誰もが思い当たる、「こどもの食」にまつわるお悩み。
「どうしたらいいのかな」と一人で抱えていたら、ブルーになっちゃう……。そんなときは、まわりの人にどんどん相談してみるといいかも!
今日は特別に、
子育てと教育学のスペシャリスト、汐見稔幸先生に相談してみました。
お悩みはこちら!
「こどもがかなりの偏食です。どうすれば嫌いなものを食べてくれるでしょう?」来ました、切実なお悩み……。先生、そもそもこどもの好き嫌いってどうしてあるのでしょう?

汐見先生「じつは
こどもの好き嫌いって、命を守るための本能なんですね。わがままでもなんでもありません」
え、本能……? 好き嫌いがあるのは当たり前ということですか?

汐見先生「そうそう、
こどもにとって『食べる』ということは、体に異物を取り入れることといえるんです。舌にある『味蕾(みらい)』というセンサーが、口に入れた物の味を確認して体に入れていいものかそうでないのかを判断するんですが、その味覚センサーは大人よりこどものほうが発達しているんですね」
そうなんですか。よちよち歩きのこどもでも、味覚のセンサーは大人より敏感ということなんですね。驚きです!
「こどもは味にとても敏感で、とくに初めて食べるものには味覚センサーがフル稼働します。
苦手な食べ物があるのも当たり前なんですよ」
はぁ~、好き嫌いが当たり前、とうかがってちょっと気が楽になりました。大人になるにつれてだんだん食べられるものが増えてくるんでしょうか。

「はい。それはなぜかというと、
〈食の体験〉がカギなんです。いろいろなものを食べることによって、味覚センサーが多様な味を感知、分析して受け入れられるようになってくるんですね。だから、
嫌いなものを無理に食べさせようとするのは逆効果。嫌いと感じる味を好きに変えるような〈食の体験〉が大切になってくるんです」
食の体験……

「例えば、自分で野菜を育ててみたり、畑で収穫体験をしてみたり。捕れ立ての魚やしぼりたての牛乳を味わったりするのもいいですね。自分で料理を作ってみるのも、とてもいい!
楽しい体験とともに味わうことで、苦手だったものがすんなり好きに変わることも多いんですよ」
汐見先生、ありがとうございました!
先生によると、いつもよりじっくりと、家にある野菜や肉・魚を観察してみたり、親子でいっしょに買い物や料理をしてみることや、
体の中を食べ物がどんなふうに通るのか想像してみたり、
外国ではどんな料理を食べているのか調べてみたりする、
なども「楽しい〈食の体験〉」になるのだそう。

夏休みは、冒険気分でそんな食の体験をたくさんしてみましょう。
たとえ旅行やレジャー施設に行かなくても、わくわく胸が躍れば、
それは冒険!
楽しい体験を重ねて、いつのまにか好き嫌いが少なくなったら、万々歳ですね。
 汐見稔幸先生
汐見稔幸先生東京大学名誉教授。専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。NHK Eテレ「すくすく子育て」などでおなじみ。自身も3人の子育てを経験。全国のママ・パパの育児の応援団長をめざしている。
(『楽しく食べれば、生きるチカラが身につく! こどもオレンジページ No.3』より)
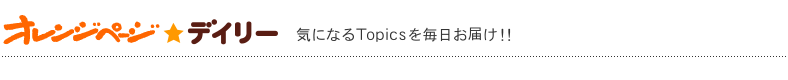
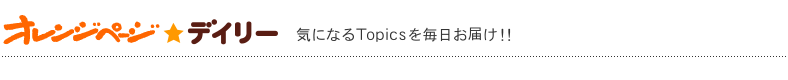


 汐見先生「そうそう、こどもにとって『食べる』ということは、体に異物を取り入れることといえるんです。舌にある『味蕾(みらい)』というセンサーが、口に入れた物の味を確認して体に入れていいものかそうでないのかを判断するんですが、その味覚センサーは大人よりこどものほうが発達しているんですね」
汐見先生「そうそう、こどもにとって『食べる』ということは、体に異物を取り入れることといえるんです。舌にある『味蕾(みらい)』というセンサーが、口に入れた物の味を確認して体に入れていいものかそうでないのかを判断するんですが、その味覚センサーは大人よりこどものほうが発達しているんですね」



記事検索